|
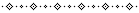
時間さえあれば筋肉痛は確実に治る。
が、が心身に抱え込んだ疲労は甚大で、精神力で補えるようなものではなくなっていた。
どの道、が戦場に駐屯するには、もう無理があったのだ。
一分一秒でも早く、を居城へ帰らせるべく本陣から送り出したいと焦る軍。
そんな軍を執拗に攻撃して、試みを阻み続ける毛利・北条連合。
それぞれの思惑を胸に、戦は小競り合いが続くばかりになった。
互いに動向を伺いながら一進一退を繰り返し、一年が過ぎ、二年が過ぎた。
長期に渡る戦は双方にとって不利益にしかならない。ならばやりようによっては休戦調停に持ち込めるかもしれないとは期待していたようだが、その思惑は見事に外れた。
毛利・北条連合が物資や兵力でジリ貧になることはなく、何よりも毛利隆元は意固地になっていた。
圧倒的な兵力・財力を擁す毛利家が極限状態にある家を相手に圧勝を勝ち取れない。
奇妙な策により大敗を喫し、捕縛策も仕損じた。
何の戦果もないまま格下の女子が率いる国を相手に休戦協定を結ぶなどという結末は、彼にとってはご先祖様への侮辱に相当する。
打開策を模索するまま不毛な膠着状態は続き、更に時は過ぎた。
千日戦争開幕から二年九ヶ月、戦地を囲う風が二度目の秋の訪れを告げる頃合。
「何!? どういう事だ?!」
各陣営の後方都市には予想外の変化が訪れていた。
徐々に姿を現した変化は、数の利によって優勢を確固たるものとしていた毛利・北条連合へと影を落とした。
「はっ、この地に留め置かれ続けたのが原因かと…」
本拠を二年以上も空けていた事による横やりが、毛利領に発生し始めたのだ。
元より災害復興中である領の隣国は、への侵攻を得策とは思わなかった。
それらの国々は自国の領土拡大の為に他国と争うか、千日戦争をこぞって傍観する姿勢を貫いている。
何よりもの方針で大抵の国と同盟を結び続けていた為に、領に関しては周囲の国々との間で不可侵条約が敷かれていて、それが破られる事はなかったのである。
元よりは防衛戦が多く、侵攻戦も北条との一度きりという国だ。
国主が戦国では珍しい女性であれば、後回しにしても方法次第では容易に下す事も出来るだろう。
民を案ずる風采を持つとの評判もあるし、ともすれば、この状況下でそのような国へ侵攻すること、ひいては同盟反故に踏み切るということは、天下に謗りを受ける元になるだろうとの見方が強かった。
だが毛利家はそうはいかなかった。
肥沃な土地と金山を擁し、莫大な資金と兵力を背景に独自の路線でやって来た毛利家は同盟締結は必要としなかった。
自領にとって明確な脅威となる勢力以外との同盟など、唾棄すべきものだと考えていたのだろう。
その姿勢が、余裕が、ここにきて仇となった。
ここぞとばかりに近隣諸国から攻め入られ始めたのだ。
毛利が所持する全土を掌握出来るとは、攻め入った諸公も考えてはいない。
ただ微弱であれ、領地を奪い取る事は可能だろうとの算段だ。
毛利の大隊はに釘付けとなり、兵力も削がれつつある今、この機を突かぬ術はないと判じたのだろう。
所領各地へとちょこちょこ入り始めた侵攻報告。
それを前に、毛利隆元は苦渋の決断を下す事になった。
後詰として到着していた三軍の内、立花軍を国元へと下げて、防衛に回したのだ。
手強い敵が一人でも減れば、それだけ軍にとっては好機だ。
軍はこの変化を見逃さず、迅速に動いた。
出撃した本隊が防衛線を押し上げて、遊撃隊が戦場を撹乱する。
その間に敵の目の届かぬ間道を探し出し、急ごしらえの馬車を送り出した。
一刻も早く、を戦場から脱出させようと、将から一兵卒まで、誰もが必死だった。
「残念だけど、そうはいかない」
「ッ!? むぅ、やはり来たか!!」
「今度こそ、無双の剣がおごふぅっ!!」
「……ほぅ、お前さん達かい? さんを狙ったのは?!」
間道を進む小隊の前に佐々木小次郎・宮本武蔵の二名が現れる。
官兵衛から彼らに下されている命はまだ生きていたようだ。
だが兵に守られている馬車に下がる幕を突き破って揮われたのは、一振りの鉾だった。
鉾に穿たれ、口上すら述べ終えられぬまま武蔵が大空を飛んだ。
「?!」
「こ…これ、出るのが早いぞ!!」
「そう言いなさんな。さんが受けた痛みは、俺が倍返しにしないとな」
ゴゴゴゴコ…と地響きでも起しそうな殺気を迸らせて、馬車の中から降りて来たのは、家守護神と呼ばれる傾奇者だった。彼は巨躯にものを言わせて鉾を振り回した。
「痛くても喚くんじゃねぇぞ!!」
駆け出した慶次と真っ向から切り結び始めた武蔵を尻目に、小次郎は身を引こうとする。
眼前の男と切り結ぶ事は確かに魅力的だが、彼はその前に、ともう一度見えてみたいと願うようになっていた。
が使者の力を得て、武蔵を退けた事実に強く魅かれる彼は、との再戦を果たしたくて仕方がなかったのだ。
「そうはいかぬ! 様は皆の希望!! 邪魔だてはさせぬぞ!!」
小次郎の進路を塞ぐべく、家康が筒槍を構えた。
「全く…いいよ。二人ともまとめてここで斬ってあげる」
間道での小競り合いを確認した幾つかの小隊が馬車や荷車と共に、別の間道を進み始めた。
前田慶次までもを囮に使った脱出策。
これは奇策ではなく真の撤退だと判じた官兵衛は、機動力を持つ島津豊久率いる騎馬隊に次々と小隊を襲撃させた。
目的は小隊の殲滅ではなく、敵が運び出そうとしているものの確保だ。
なかなか当たりを引かぬ豊久が焦りつつ任をこなしていると、前線の統制を預かる島津義弘の元へと長宗我部元親から伝令が走った。前線は自分が支えるから豊久と合流せよ、というのだ。
「なるほどのぅ。敵もやりよるわ。さても美しき魔女、この目で確かめに行くとするか」
島津義弘が長宗我部元親に前線の指揮を委任し、単独で持ち場を離れた。
彼が騎馬を駆って進む間道には馬車だけでなく、時差を経て進軍し始めた兵糧運搬用の荷車があった。
「鬼島津、参る!!」
義弘が木槌を奮って突進してきた。
「ちっ、きたか!!」
荷車と共に進軍していた孫市が銃を構えた。
島津義弘の兜を狙った見事な狙撃で彼を騎馬から叩き落とす。
だが体勢を整えた義弘は脇目も振らず、駆け続けて、ついに荷車へと手を掛けた。
ぱかぽこと間道を進んでいた馬が豪腕に引き留められて宙でたたらを踏む。
荷車に傾斜が生まれて、積んでいた砂入りの兵糧袋が転げ落ちた。
その隙間に見た白い足首を、義弘は迷わずに掴んだ。
「御免!!」
「ッ!! 痛ぁい!!」
息を殺してやり過ごすつもりだったが、豪腕に握られてはひとたまりもない。
が咄嗟に声を上げた。
「おい、調子に乗るなよ、ジジイ!!」
孫市が激昂して義弘の腕を銃身で打った。
義弘が荷車を力任せに引き倒してから距離を置く。
「ほぅ。噂通りの美しさよ。我が陣へ連れ行く故、しばしそこで大人しくしていられよ」
女相手に手荒な事をするつもりはないのか、義弘は孫市へと向かい、身構えた。
「心掛けはいいな、じいさん。だが年寄りの冷や水は命を縮めるぜ」
「…いらぬ心配よ。それよりも小僧、鬼島津とやり合うにはちと早くないか」
「無駄口叩けなくしてやるぜ!!」
義弘の後方で尻餅をつくと視線を一度合わせると、孫市は小さく頷いた。
それで彼の意思を汲み取ったは、懸命に両手を大地について立ち上がった。
片足を引き摺りながら歩き始める。
義弘がちらりと視線での背を確認し、再び孫市へと視線を戻す。
どうやら彼は孫市を倒した後に追ってもを捕まえられると判じたようだ。
二人が切り結び始めたのを尻目に輿の護衛を担う兵の手を借りて馬に乗ったは、駆け出した馬の首にがむしゃらに噛り付いた。馬は間道を駆けに駆けて、への道を急ぐ。
「待たれよ!! そうはいかぬ!!」
「新手か!!」
護衛を担う兵が散開し、防衛網を築いた。
その防衛網を突き破っての騎馬へと手を掛けたのは一つづつ馬車を潰していた島津義弘の甥・豊久だった。
「殿と御見受け致す、我らと共に来て頂こう!!」
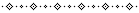
「何?! 我が君が敵の手に落ちたと?!」
前線を支え押し上げていた長政・左近・三成・秀吉を始め、遊撃隊を率いていた小六・成実ら軍諸将の間に激震が走った。
「孫市は何しとったんじゃ!!」
秀吉が顔を歪めて叫べば、我に返った三成と左近が同時に叫んだ。
「奪い返すぞ!!」
「長政さん、ここは任かせた!!」
二名が戦場を離脱しようとすると、彼らの背後で三味線が鳴った。
二人が焦れた顔で振り返れば、涼しい顔をして長宗我部元親が立っていた。
「何を急ぐ?」
「…急用なんですよ、長宗我部元親さん」
「邪魔だ」
「上等!! 行きたくば俺の屍を越えて行け」
「そうさせて貰おう!!」
言うが早いか三成が扇を振り翳した。
斬り込む三成の攻撃を巧みに避けながら、元親は逃げ回る。
『こいつ、時間稼ぎか?!』
三成が舌打ちして互いの間合いを調節しようとすると、元親は薄く笑った。
敵の狙いに気がついた左近がアーツで牽制し、元親の動きに一時の間を作る。
そしてその隙に三成の肩を掴んで後方に引き倒した。
時同じくして、三成のいた場所に知らず知らずの内に散りばめられていた気泡が爆ぜた。
「くッ! すまぬ、左近」
「いいえ、こんなの年の功でしかありませんよ」
「…ふふ、なかなかやるな…」
「どうも。だがあんたの相手をしてる暇はないんですがね」
左近が大太刀を構え直した。
「殿…ここは俺が引き受けます。姫を頼みます」
「…分かった、任せろ」
身を引こうとした三成の前に、長宗我部信親と盛親が立ちはだかった。
「そうはさせぬ!!」
「チッ、次から次へと厄介な…」
二人が長宗我部軍の包囲網の中に落ちた事に気がついたのは、今になってからだ。
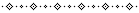
「…万策尽きたか…」
完全に旗色の悪くなったに巻き返しの風が吹いたのは、その日の夕刻。
島津豊久の騎馬がを伴って、毛利本陣を目指し間道を走っている最中の事であった。
豊久が駆ける間道の一つ上の山道で、ホラ貝が響いたかと思うと、新たに一軍が現れた。
毛利・北条連合に動揺が走ったのは、その軍を率いているのが豊久に捕えられているはずのだったからだ。
「役目御苦労、もう死してよろしいですよ」
新たに現れた軍勢を率いるの傍に立つのは本国守護名代であるはずの竹中半兵衛だ。
彼は指揮丈を振り翳し、豊久の手に捕えられているへと向かい、淡々と言った。
豊久だけでなく、が混乱して息を呑む。
「弓兵よ、矢を射かけよ!! かような者、いくらでもいます!! 豊久の首をとる方が大事です!!
構いませぬかな? 様」
輿に誂えられた席に座したままのに問えば、は小さく微笑み頷いた。
すると半兵衛は、怜悧な笑みを口元に浮かべて指揮丈を振り下ろした。
「なんと!! 私は謀られたのか!!」
|