|
ゆるりゆるりと、意識は沈んだ。
体が冷えきり、感覚を失っていく。
詰まる呼吸。軋む体の節々。
掴まえられる物を求めて振り回していた腕には、今となってはもう動かせるだけの力が残ってはいなかった。
ぼやけ始めた視界の中には無数の泡が散らばる。
その泡の量に不安になりながら、一方で美しいと思った。
『…こんなところで……終わるの?
私の人生は……こんなところで……終わってしまうの…?』
有名になりたいとか、お金持ちになりたいとか、特別なことを求めている訳ではない。
求めている訳ではないが、こうして己の命の灯火が弱まってゆくのを実感すると、ちっぽけな命でも惜しく思えた。
『もっと、がむしゃらに生きればよかった……もっと……色んなことをしてみればよかった…』
既に心は諦めの境地。
助けを求める事よりも、漠然とした悲しさに満たされている。
『もし、もう一度……生まれ変わる事が出来たなら…………今度は……もっと…もっと別の生き方を……』
深海に沈んで行く彼女の視野を、柔らかな光が掠めた。
突然現れたその光に包み込まれると同時に、息苦しさが幾分か和らぐ。
自分を包んだ光はとても柔らかく温かい。
漠然と"生"とはこういうものなのではないかと思った。夢心地だった。
『…その願い……聞き届けよう…』
『…温かい……ここは、天国? それとも……私は、まだ生きているの?』
物事を冷静に判じるだけの余裕を失った中でした自問自答。
それに対する答えは、彼女を包み込んだ光の中に現れた老人が与えてくれた。
『…まだお前は生きている……… 今一度、問う。
お前は、今一度"生"を繋ぐ為にやり直したいのか? 』
彼は悲嘆にくれ、疲れ果てた眼差しをしていた。
何故そんな眼差しをするのかが分からず、不思議でならなかった。
ただその老人の眼差しは、彼女の感情よりも魂に語りかける強さを持っていた。
『……もしここで、今一度……時間を与えたら……お前はやり直すことを誓ってくれるのか? 』
『うん、いいよ……私に出来るならね、なんでもやっちゃうよ?
悪いことではなければね…… 』
柔らかく温かな光に誘われるように、意識はまどろむ。
どの道最期だ。これは走馬灯にも似た甘美な夢なのだろうと、彼女はあまり深く考えずに答える。
『…そうか…では…汝にチャンスを与えよう……。
今一度…"生"を繋ぎ……あの世界を、導くチャンスを…… 』
『…はーい、期待しないでね…』
老人の言葉を最期まで聞き届けることなく、意識は闇の中へと沈んだ。
彼女の体は神々しい光と共にゆるりゆるりと深海の奥底へと吸い込まれて行く。
『時空の扉は、今、こうして開かれる』
老人は歪む海面を通して空を仰ぎ見た。
そこには広がる快晴の空。白い雲。
どこにでもある穏やかな風景を、彼は眩しそうに眺めて涙する。
『…異界の娘よ……我らの未来に…どうか、平穏を…』
老人が呟くと同時に、彼女を救った光は、海の奥深くで消失した。
時を同じくして。
「こりゃまた不可思議な取り合わせだねぇ」
「全くだ、あんた方もあの声を聞いたんで?」
「ええ、お二人も…ですか?」
寂れた城の天守閣、無人の上座を前に、三人の男が佇んでいた。
それぞれ個性溢れる装いで、一見して彼らに繋がりがあるとは思えない組み合わせだった。
「幸村、お前さんは何をどう聞いた?」
2mはある巨躯を持つ度派手な装いの男が問えば、赤一色で揃えた鎧に身を包む若武者がハキハキと答えた。
「今日の日没と同時に、この城に来いと。さすれば私を導き、世界を変える方に出会えると。
その方の刃となり、盾となり、補佐をするのが私の宿命だと聞きました」
「ほぅ、そうですか。俺は、軍師を努めろと言われましたよ」
左頬に傷のある長髪の男が混ぜ返すように言えば、幸村は自分が受けた質問を派手な装いの大男へと返した。
「慶次殿は?」
「俺かい? 俺は、護衛だとさ。一緒にいりゃ、大層面白い経験が出来るそうだ」
「信じてるんですか? 二人とも」
傷男からの問い掛けに、幸村は頷き、慶次は顎を掻く。
幸村と違って、彼や慶次は半信半疑のようだ。
「お前さんはどうなんだい? 左近」
「…さてねぇ、こんな世の中だ。
この左近の軍略を生かせる器であれば、考えてみてもいいが…ね」
三人の会話が一段落すると同時に、日が落ち始める。
「さて、どうなるか見物だな」
部屋の中に持ち込んだ行灯の火がゆらゆらと揺れる。
破れた障子の向こうから吹き込んだ夜風に撫でられているのだ。
語る事を止めた男三人を取り巻くのは、静寂。
やがて静寂は緊張を呼んだ。それは時間が経てば経つほど、深く、色濃くなる。
けれども目に見えるような変化は、なかなかこの部屋の中には現れない。
暫くすると、三人は焦れ始めた。
「…大の男が三人揃って、狐か狸に化かされましたかね」
左近が独白している間に、ついに日は落ちた。辺りに夜の帳が降りてくる。
空気が冴えて、冷え込み始める。静寂の中に夜の虫のリリリリ…と鳴く声が混じるようになる。
月が大陸の向こうから姿を現して、天を目指してゆっくりと昇り始めた。
「時間の無駄でしたな」
最初に神託を見限ったのは左近だった。
彼は大きな刀を肩に乗せると、身を翻し歩き出そうとした。途端、彼はその場で息を飲む。
「お二人さん、あれ…どう思いますか」
「どうしたい?」
「どうかしましたか?」
問われて残された二人が同時に振り返れば、天に昇り行く月は、紅蓮に染まっていた。
「おいおい、こりゃ一体…」
三人で呆然と月を見上げている間に、月は黒く変色し始める。
「馬鹿な!! 今宵は月食じゃぁないはずだ!!」
肩から刀を落として、左近が叫ぶ。
声に出さないまでも驚いていたようで、幸村は身を乗り出して月を凝視していた。
刹那、外から室内へと突風が吹き込んだ。
部屋の中へと入ってきた風は、まるで生き物のようだった。
下座から上座へと並べられた蝋燭の明かりを撫で斬りにした。
部屋の中にある全ての灯りを、下座から上座へと向かって、それも交互に、順序立てて消し去る。
これは、まるで予兆だ。何者かを呼び出す儀式のようではないか。
「まるで怪談だな」
風の進行を視線で追えば部屋中を流れた風は、上座に灯した行灯の中の光すらも消し去って、そのままそこで費えた。室内に完全な暗闇を齎したのだ。
「随分とまぁ、凝ってるねぇ」
軽口を叩きながらも彼らの目に油断はない。
彼ら三人は、自ずと愛用の武器に手を伸ばし、何時でも抜き放てるようにと身構える。
天に座す月からの光はなく、持ち込んだ灯りも意味を成さないとなれば、不安や警戒心が湧き上がってくるのは当然だ。
「慶次殿!!」
幸村に名を呼ばれて、慶次は目を見張る。
左近もまた、固唾を飲んだ。
彼らの視線の先、上座の空中には突如として不自然な歪みが現れる。
バチバチと不可解な音が鳴ったかと思えば、辺り一面に稲光と思しき閃光が走った。
三人は身を捩って辛うじて避けた。
互いに目配せし、連携を考え始めた彼らの視界に、また不可思議な現象が入る。
それは、宙を漂う黄金色の微粒子の発生。
「これは…一体?」
その黄金色の微粒子は不思議と温かく、心地よいものだった。
それが彼らを取り巻き、そして下座から上座へと向けて流れる。
微粒子の出所はと言えば、闇に食い尽くされた月だ。
少なくとも、彼らにはそう見えた。
「月の…加護ってやつかい?」
「一体、何がどうなってるってんだ…」
臨戦態勢を維持する彼らの前で黄金色の微粒子は、歪みの中央へと向かいゆるりゆるりと動く。
かと思えば、今度は突然、歪みの中心から柔らかい光が溢れ始めた。
徐々に強くなる光の中で、何者かの姿が浮かび上がってくる。
「…本当に降臨するってのかい?!」
半信半疑だった神託の信憑性を痛感したのか、慶次が目を爛々と輝かせる。
左近、幸村は息を呑んだままだ。
何者かの降臨は、頭部と爪先がまずはっきりと現れ、続いて肩が、踝がという流れだった。
やがて微粒子を纏い、光の中から浮かび上がった人影は、一人の女性の姿を形どった。
「なっ! 女性?!」
幸村が最初に大きく反応した。
彼はこの瞬間まで自分を導く者が女性である可能性を微塵も考えていなかったようだ。
「そんな…我らを導くのは、女性だというのか…?!」
「これじゃまるで天女降臨だな」
動揺を露にする幸村の隣で構えていた左近は、彼女に意識がない事を見取ると構えていた刀をその場へと降ろした。
彼女が降臨すると同時に、月光が戻り、続いて室内の蝋燭にも火が戻った。
黄金の微粒子もとうに掻き消えて、彼女の降臨の余韻は何一つこの場には残っていない。
彼らの中で唯一、女性である事について無反応だった慶次。
彼だけが、不信感も疑惑も抱かずに、目を閉じたままの彼女へと向かい、歩みを進めていた。
慶次が空中に横たわる女性へ向かって掌を差し伸べれば、現れた女性はそのまま彼の腕の中へと静かに納まった。
「これはまた魅惑的というか、恥じらいがないというか、面妖と言うか…」
明るくなった部屋の中、巨漢の慶次に抱かれると一層小さく見えてしまう女性の装いは、なんとも形容し難いものだった。羽衣のように薄い布を身に纏ってはいるが、その下は、局部を隠す場所にだけ布を纏っているという状態だ。
彼らの時代、常識、価値観からしたら、到底正気の沙汰とは思えぬ姿ではある。
露になる体から目を逸らして顔へと視線を向けた。
黒く長い艶やかな頭髪が、彼女の顔を一際小さく見せる。
唇は桜色。整った睫。目・鼻・口の造形もよく、一目で見て「美しい」と形容したくなる。
「不思議なもんだな」
左近の独白に、反意を示す者はない。
それもそのはず、面差しからは、妖艶さは感じられない。
なのに、この衣装。どうしても解せない。
官能的な衣装から伸びる白く細い手足は、華奢な印象を際立たせる。
一方で胸元から腰に掛けての曲線は、彼女が既に大人の女である事を指し示す。
率直な感想として、男の目から見れば彼女は魅惑的だ。
けれども彼女は、頭髪だけではなく、全身に水気を帯びて、微弱な冷気を帯びていた。
「魅力的な人ではあるんだけどねぇ…」
油断は出来ない。
見惚れるなんてもっての外。
それをしてしまえば、寝首でも掻かれるのではないかと疑心が募る。
意識がないだけ。生きている事は微かに波打つ胸元を見れば分かる。
けれども起こしたいとは、どうしても思えない。
「……慶次殿…」
「気絶…してるみたいだねぇ…」
夢でも幻でもないと慶次が呟けば、左近が動いた。己の陣羽織を脱いで彼女を包み込む。
彼の配慮を受けた慶次は、粗相がないようにと細心の注意を払いながら畳の上へと彼女を横たえた。
「幸村、火鉢頼めるかい?」
「え、あ! そうですね、借りてきます」
慌てて天守から飛び出して行く幸村とその場に残った慶次、左近の耳に、彼らを導いた不可思議な声が再度響いた。
"ゆめゆめ忘れることなかれ、汝らの命は、この者と共にあり"
"日の本の命運も、これまた、同意なり"
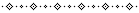
「…ん……っ……」
夜が明けて行くと同時に、肌寒さを覚えた。
あれほど感じていた胸の苦しさや体を縛る痛みは消えていて、今はただただ、ひたすらに肌寒い。
覚醒した脳は、このままでは風邪を引くと警鐘を鳴らしている。
起きたいようで起きたくない。起きてしまえばまた日常が始まる。
好きな仕事ではあるけれど、忙しない日々が、また始まってしまう。
もう少しだけ、あと少しだけ、休日の余韻を味わっていたいと、意識は葛藤を繰り返した。
『…あー、そうも…言ってられないか……支度、早くしなくちゃね…』
毎日している葛藤に終止符を打って、彼女はゆっくりと閉じていた瞼を開いた。
まだぼやけている目を擦りながら、身を起こす。
「あ……れ?」
定まらぬ視界で得た情報は、己が想定していた光景とは全く別の景色を映し出していた。
咄嗟に記憶を遡り、自分が海で溺れた事を思い出す。
とすれば、日常と異なる景色を目にするのは当然の事。
だとしてもここは海岸でもなければ、病院でもなく、ましてや海の家でもない。
視覚的要素が、それを容易に教えてくれているから、間違いない。
「…………えーと?」
眼前に広がるのは、襖と屏風。
古びて痛んでいるとはいえ、随分と細かく丁寧に書き込まれている模様から結構な値打ちものなのではないかと思われる。それが己の視界を埋め尽くしている。
「……んー…と…」
理解が及ばない。
何がどうしてどうなった?? と、その場に座ったまま首を傾げて、頭を掻いた。
そんな彼女の背後から、遠慮がちな声が掛かった。
「あ、あの…」
「え?」
他に人がいた事への安堵と、少しの驚きと共に振り返った。
そこには、自分の常識では到底許容出来ない装いの男が三人座していた。
一人が正座、後の二人は胡坐だ。
「…………えーと……?」
どんな二の句を次げばいいのかと、思い切り困惑を顔に貼り付けたままでいると、顔に傷のある男が吸っていた煙草の吸殻を火鉢の中へと捨てて、煙管で彼女の事を指し示した。
「すみませんがね、そろそろ、隠してもらえませんかね?」
「え?」
示されて、己の姿を見れば、間違いなく海で溺れた時と同じ装いだった。
すぐさま身の危険を自覚して、掛けられていた男物の衣で体のあちこちを隠す。
「あ、あの……ええと、その……お世話になりました」
上擦った声のままジリジリと後退する姿に、正座していた若武者が慌てる。
「か、勘違いなさらないで下さい!!
私達は、貴方の家臣です!! 貴方を害そうなどとは思ってもおりませんっ!!」
「は、はぁ? えーと、なんのドッキリですか? それとも、なりきりかなんかかな??
良く分からないけど、そういうのはどうぞ他所で…」
「ドッキリ? なりきり? それは一体…??」
「ええ? 違うんですか?! じ、じゃぁ…何が目的で…?」
互いに混乱しているのは明白だ。
そんな二人のやり取りを静観して面白がっている派手な装いの男に、若武者は視線で助けを求めた。
「おや、幸村はもう降参かね。もっと奮戦してくれると思ってたんだが」
カーニバルでもあるまいし、一人でこんな派手な格好をしくさって。
大方常識人ではあるまいと思われるこの男に、どうして話を振るのかと内心で焦った。
少なくとも、柄の悪そうな傷男や、このカーニバル男よりも、この若武者の方が、まだ話が通じそうだったのに。
これでは益々訳が分からなくなるではないか。
「慶次殿、頼みますよ!!」
「仕方ないねぇ」
豪快に笑うカーニバル男と赤面して固まりまくる若武者。
彼ら二人の間に座る煙管男は、未だに鋭い視線で彼女を観察している。
これでは逃げ出そうにも逃げ出しようがない。
しかもこんな大柄な男達を前に、下手に抵抗して機嫌でも損ねたら、本当にどんな目に合わされるか分かったものではないと、彼女は引き攣り続ける。
そんな彼女に、若武者の願いを聞き届けたカーニバル男が問い掛けた。
「なぁ、お嬢さん。あんた、最近妙なじーさんの声を聞いた事はないかい?」
「お年寄りの??」
仕事柄毎日接しているが、どのおじいさんの事だろうと、己の記憶を探った。
これはもしかしたら暇を持て余した有閑老紳士の仕組んだ遊びなのかもしれないと、藁にも縋る思いだった。
「ああ、"日の本を制しろ"とかな」
「そんな要求は特には…」
「そうかい? 言い方を変えてもいいんだぜ」
「言い方ですか?」
「ああ、"天下を治めろ"とか"導け"とかな」
記憶を漁り、そこでふと、気が付く。
「"導く"? "あの世界を導く"? チャンス……え、あ、あれって……夢、じゃなかったの?!」
目を丸くした彼女の脳裏には、水没して行く自分が見た不可思議な光景がありありと蘇っていた。
|