|
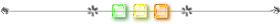
さて、ここで話を少し巻き戻してみよう。
大谷吉継が気を利かせてと三成を二人きりにした日。
が戻って来た吉継に対して怒りを爆発させて泣いたのには理由がある。
寂しいとか心細いとかいう理由ではない。
ぶっちゃけは、士官を断った時に自分が口にした予感を見事に的中させてしまって、その事実に嫌気がさしてブチ切れたのだ。
それ即ち、嫉妬。
そして陰湿なイジメである。
大谷吉継と石田三成という性格にやや難ありではあっても豊臣家きっての美男子二人に、は常に構われている。
更に兄貴面が板についた清正や友人としての地位を確立させつつある幸村と利家にも何かと目をかけられている。
この事実が、の同僚となる内政官ではなく、女中達のやっかみを買った。
当人の望む望まないに限らず、依怙贔屓を受けている鼻持ちならない女扱いのは、廊下を歩くだけで、女中達に無意味に笑われたり、陰口を叩かれたり、無視をされたりと陰湿過ぎる嫌がらせを受けていた。
例の二人きりにされた日など、三成が部屋を去ってからが酷かった。
資料を探しに書庫へ出かけている間に、閉じ込められる。草鞋に針を仕込まれる。
挙句、作った書面は男性用の厠に捨てられていた。
正則が見つけて「風で飛んだんじゃないのか」と言われたがそんなはずがなかった。
吉継の執務室と男性用の厠の距離を考えてみろと、流石に愚痴りたくなったである。
一度取り組み方を教えられたから、作り直す事自体は簡単なのだが、再び取り掛からなくてはならないという労力と、これまで費やした時間を無駄にされたという疲労感が心にしんどい。
そして困り果てるを見て気持ちよさそうに、ざまぁ見ろとばかりに口元を歪めて嗤う女達の執念が気色悪い。
追い出したいのだろうな、というのはよく分かっている。
寧ろ職を辞してかつてのような気楽な生活に戻れるものなら、戻りたい。
だがを構い倒す美丈夫二人がそんな選択を許すはずがない。
女同士のいざこざを吉継や三成に相談するのもなんだか悔しいし、二人が何かしら動いたら動いたで、火に油を注ぐような気がするから二人には何も話していない。つまるところ、八方塞がりだ。
吉継や三成がいる所でやられるわけではないから、どうしても身を護る為に二人のどちらかの後をついて回ってしまう。それでまた嫉妬される。完全な悪循環が出来上がっていた。
「大丈夫でしょうか…殿…最近なんだか元気がない様子で…」
「はてさて…こればっかりはねぇ……」
の変化に気が付かぬ者ばかりではない。
幸村や左近などは女達の醸し出す嫌な雰囲気に気が付いている。
幸村には理由が分からないから困惑するしかなくて、せいぜい声をかけて気晴らしに連れ出してやるくらいしか出来ない。一方で左近はおよその憶測は付いているのだが、幸村が察しよくフォローに回っているので自分まで手を出すと、更にへの当たりを強める原因になりかねないから動くに動けない。
『女子同士の話となるとな……これ以上続くならおねね様を担ぎ出さないと不味いですかね…』
時間を合わせての退出時に幸村を誘い下町に繰り出すのは、のガス抜きもあるが、もう一つ理由がある。
唯のやっかみや嫉妬が仕事上の出世欲と絡んだ場合、面倒なことになる。
例えばを毛嫌いする女中の誰かが、腕に覚えのある単細胞を抱き込んで帰りに襲わせないとも限らない。
エスカレートしてしまう事態を想定して、左近、幸村、清正、正則、利家が代わる代わる送っているのだ。
「はぁ……宮勤めなんてやっぱ向いてないよな〜」
は頭の回転が速いだけでなく、なかなかしぶとい。
嫌がらせされてもめげないというか、平然を装うのに長けている。
舞台に立つ者独特の性なのか、有事でも笑顔でその場を切り抜けることに慣れ過ぎているのだ。
嫌がらせを受けて困惑したり泣いたりすれば、首謀者の気も少しは晴れるのかもしれない。
が、は泣くよりも駄目にされた物は早急に作り直さねばならないと、意識を転換してしまう。
勝手な話だが、嫌がらせしたのに相手にされず、サクサク意識を切り替えられると、やった側としては馬鹿にされたような錯覚を抱くものだ。にしてみたら言いがかりも甚だしくて傍迷惑な話なのだが、嫌がらせする側にの思考など分かるわけがなかった。
舞台に立つの気分転換に付き合いつつ、なんとか誤魔化し誤魔化しやり過ごす日々。
首謀者だけでもあぶり出せないかと目を光らせる左近が、気だるげな雰囲気を前面に押し出して、彼に気のある女中衆にちょっとカマをかけてやれば嫌がらせの発端と原因が見えてきた。
「吉継様付きの女中頭様がちょっと…ねぇ」
「え、ええ…今までは吉継様のお傍に寄り添う女性など、いなかったものですから…」
軽く調べてみたら、吉継に仕える女中頭は武家の娘で、それなりに美しいが、気位の高い女だった。
その気位の高さが仇となり、いい年になっても縁談が纏まらなかったようで、ならば職場結婚を…と親が充て込んで城内の女中に志願させたのだ。
一介の武将からの求婚を跳ねのけるだけあって彼女は呑み込みも早く、女中達を取りまとめる器量もあった。
人望ではなく恐怖政治で治めている辺りがなんとも言い難い感想を抱かせるが、標的にされぬように過ごせばいいだけだと、仕える女達は諦めにも似た惰性で勤めをこなしている。
そんな女が、身勝手に夢見たのが自身の主、大谷吉継からの寵愛を受ける事だった。
影に日向にと気を使い、あの手この手で彼女はアピールしたが、大谷吉継には他所に心に決めた人がいるのか、見向きもされなかった。
それでも良かったのだ、これまでは。大谷吉継の心を奪う女は他になく、傍で粛々と務めれば、涼やかな笑みを持って労われるのは、自分だけだったのだから。
「本日より俺の副官となる、宮仕えは初めてだから皆補佐をよろしく頼む」
「えーと、よろしくお願いいたします〜」
それが、突然変わった。
合わせ蝶の紋を刻んだ詰襟の羽織を与えられたうら若い乙女が、大谷吉継の傍に立っている。
彼女を獲得するまで吉継がした苦労はこれまでに類を見ないもので、時には目の下にクマまで作って頭を悩ませた。
まるで恋に苦しむかのように連日連夜徹夜して、挙句には倒れたくらいだ。
当然、今まで以上に、吉継は傍仕えになど目を向けなくなる。
女中頭の自尊心はいたく傷つき、想い人の興味を掻っ攫った若い娘への嫉妬と憎悪を生んだ。
二人は恋仲でもなんでもないのだから、巧い事を取り込めば、橋渡しをして貰えたかもしれないのに、無謀にも彼女はを追放する道を模索し始めてしまったのだ。
「町で下品な踊りをするだけあって、凄いわよねぇ。
吉継様だけじゃなくて三成様まで誑し込んでるみたいよ」
憶測と妄想を決定として風潮すれば、三成に恋焦がれる女中衆が彼女の味方になった。
実情は三成が一方的にに懸想しているだけだ。
吉継の周りの女中達を気にすれば良かったはずが、三成の周りの女中達まで警戒せねばならなくなって、は日に日に疲弊した。
「2.3.5.7.11.13.17.19.23.29.31.37.41.43.47.53.59.61.67.71.73.79.83.89.97…」
「え、なんですか…その呪文みたいなの…?」
がブツブツと素数を数えて気を紛らわせるようになった辺りで、流石に左近、幸村、利家はヤバいと思い始めた。左近、幸村はの精神状態を案じたが、利家は別の可能性に冷や汗を流した。
その日、が堪忍袋の緒を自ら引き千切った日。
利家がねねを訪ねて、事情を話してねねの助力を得ることに成功した日。
残念なことにねねが動くより先に、の怒りが執務棟の中で爆裂した。
「すまねぇな。わざわざ出向いてもらってよぉ」
「いいんだよ〜。こういうことはあたしにお任せだよ!」
黄色の着物の袖をなびかせて、ねねが利家と共に吉継や三成が詰める執務棟へやってくる。
「私も三成のいい人に会ってみたかったしね。楽しみだよ〜。どんな子」
「っざっけんじゃねぇぇぇぇぇぇぇぇ!!!!!!!!!」
ねねの言葉は続かなかった。
正に怒髪天。マイクもなく舞台で数多の観客を魅了する声量を持つの怒声が執務棟の廊下を突き抜けた。
続いて利家とねねの目の前を駆け抜けたが、女中の一人をとっ捕まえて投げ飛ばした。
「いい加減にしろよ、クソ女ども!!!!!」
ビンタではない。髪を掴むのでもない。
藻がビッシリ生えた中庭の池目がけて、豪快な大外刈りだった。
『ああああああああああ!!!!』
遅かったと頭を抱えたのが利家。
絶叫に驚いて廊下に出てきたのが左近、幸村、吉継、三成、清正だ。
「毎日、毎日、毎日馬鹿の一つ覚えみたいに嫌味と無視と中傷と嫌がらせ!! 他にすることないのかよ!!!」
周囲の目も気にならないのか、はキレッキレだ。
「お前ら姑か!! 小姑か!!!」
池に叩き込まれた女中が呆然としている。
首謀者ではなく取り巻きの一人だったようで、真の首謀者は多くの女中達を従えて廊下で佇んでいる。
首謀者―――女中頭はの暴走を見て、最大の失態を引き出したと薄く笑っていた。
「なんだ? 一体?」
「どうした?」
目を瞬かせる吉継や三成の問いかけに答えることなく、は肩で息を吐いた。
誘拐騒動の時、番頭を問い詰めたを見ている利家は、の本質に恐ろしく残酷な面がある事を知っている。
は彼女の感覚の中で生死を別つ状況に追い込まれると豹変する。
舞姫、算術士、素朴な一人の女。
色んな表情を持つが、が生死の境目だと感じた瞬間、それは覚醒する。
「分かったわよ。そっちがその気ならもう我慢なんてしない。容赦もしない。全力で叩き潰してやる!!!」
戦場に身を置く者からするとのキレる過程は、非常に分かりやすい。
の中には独自のランクがあって一段階づつそれを登り、頂点に達すると生死の境目に直面したかのように、慈愛とか手心とか遠慮といった感覚が消失するのだ。
その消失が齎すものが何なのかといえば、単純明快で、殺すか殺されるかの二者択一だ。
「あー、これあれだな…もう駄目なやつかもしれねぇな…」
遠い目の利家の前では仁王立ちだった。
そして呆然とする女の頭を引っ掴むと、周囲の目もお構いなしに、池の中に沈めた。
「ちょ!! ちょっと!! 殿!!」
「お、落ち着け、どうした! 何があったんだ!」
城の中で殺人は不味いと、幸村と清正がすっ飛んできて引き剥がしにかかる。
二人を振り払いながらは吠えた。
「これくらい生温い!! 目測謝った!! 本当なら池の淵の岩で頭、カチ割ってやるはずだったのに!!
あんたね、いくら私が気に入らないからって嫌がらせするにしても、皆で使う一冊ぽっきりの資料を馬屋の
馬糞の山の中に沈めるってどういう了見してんのよ!!! 使い物にならないでしょうが!!!!」
三成と吉継が顔色を変えた。
廊下の隅には騒ぎの発端となったらしい見るも無残な書物が一冊放置されている。
「これがないと徴税の清書できないんだよ!!
清書できないってことは民の生活に多大な迷惑がかかるの!! 分かる!?」
上半身の左右を清正と幸村に抱え込まれているから足が出る。
は池の中に座りっぱなしの女中目がけて水面を蹴りまくった。
「なんてことしてくれんのよ!? この始末、誰がつけると思ってんの!?」
二人がかりでを池から引き摺り出して距離をなんとか置かせる。
清正と幸村の腕を振りほどいたが、池の中で震える女から視線を外した。
「ちょっとあんた」
が見たのは原因を作りながら、全ての失策や無礼は下に押し付けるつもりのあの女中頭だった。
「なんでございましょう?」
言い逃れするつもりの女中頭は涼しい顔のままだ。
暴れたの方が心象を落としたに違いないし、自分が裁かれる理由はないと、女中頭は高をくくっていた。
だが、今までそうやって彼女がいびり追い出した者達と違って、今回標的になったのはあのだ。
彼女の思い通りになるはずがない。
「何涼しい顔してるの。この女はあんたの部下なのよね」
「はい、申し訳ございません」
決して膝は付かずに口先だけの謝罪だ。
利家がぶるりと一つ身震いした。それもそのはず。
戦場で研ぎ澄まされた利家の第六感が、の怒りが一段回膨れ上がったのを察知したのだ。
今やの怒りはヒステリーを越えて、殺人をも辞さない生死の境モードへと突入していた。
「じゃ、あんたが責任取りなさいね」
の目は冷えに冷えて、ゴミでも見るような蔑みに満ちていた。
そんな目を向けられたことのない女中頭が、不快感で顔を顰めた。
「あんたの部下なんでしょう? なら監督責任よね?
連帯責任であんたの部下もまとめて責任取らせるからそのつもりで」
「どのような権限が貴方様にありましょうか?」
その言葉を待っていたと言わんばかりには笑った。冷笑だった。
「あるわよ。権限。この際だから、はっきりさせておきましょうか?」
庭を横切ったは縁側に腰をかけた。
「私、吉継さんと三成さんに招致されたんじゃないのよ。
私を招致したのは、あの豊臣秀吉なの。そこんところ、分かる? 私、女だけど愛人じゃないの。
あんたのような一介の女中でもないのよ」
女達の顔色が変わった。
「私はね、いわば竹中半兵衛や黒田官兵衛と同列なのよ」
「世迷言を」
「そう思う? ならここに秀吉様、呼んで来てみる??
考えたことないの? なんで私が利家さんとまで懇意なのか。子飼いじゃないのよ、彼。秀吉様の親友よ?
そんな男が私の名を覚えていて、顔を知っていて、一緒に出掛けたりもする。なんでかしらね??」
喉を鳴らす女中頭の前では足を組んだ。
緩いスリットから膝下が覗く。
「何か大きな思い違いをしてるみたいだけどさ、あんた達女中の仕事は何? 内政官の補助よね?
で、私は内政官。あんたらに指示をする側。あんたら女中の末端に配属されたわけじゃない」
ぴしゃりと言い切ったは一息吐いた。
やり合う二人の様子を窺う女中達の喉がごくりと鳴った。
「さて…色ボケのあんた達にもそろそろ状況が読めてきたでしょうから、
あんた以外の子達にもはっきり意思確認しましょうか」
見事に誂えられた庭の玉砂利をは指示した。
「今日今この瞬間から、豊家に仕える女達の頂点が誰になったのかを理解したなら、今後はその女じゃなくて、
誰の顔色を窺って、こびて、諂えばいいか分かるわよね??
分かったら、取り合えず、そこに全員正座」
女中衆の視線が玉砂利の上へと動く。
庭師が丹精込めて誂えた庭は、秀吉のお気に入りだ。
その庭の砂利の上に正座しろとは言う。
「そ、そんな事…」
女中頭の後方に控えた女達がざわついた。
「1.2.3.…」
数え始めたに恐れおののいたのか、一番奥の廊下で御勤めに励んでいた一人の女中が声を張り上げた。
「発言をお許しください、様! 私が今運んでおります器は朝廷から賜りました一品にございます。
これを床などに下ろせば秀吉様がお咎めを受けてしまいます!!
どうかお片付けをするお時間を頂けますでしょうか!!」
派閥に属すかどうかも怪しい末端の女中が、自分よりの顔色を窺った事実に女中頭は怒りで顔を朱に染めた。
「いいわよ。それ、先に置いてきなさいよ」
「は、はい! すぐに!!」
逃げたのかと思いきや、本当にあの女中は持ち運んでいた器を蔵にしまって猛ダッシュで戻って来た。
しかも玉砂利の中央にででーんと据え置きされた岩の上に正座する。
『賢いな』
この状況でその感想はどうなんだ? と思わなくもないが、利家が抱いた率直な感想だった。
無意識であれ、そうでないであれ、据え置きの岩に彼女が腰を落ち着けた為に、玉砂利を崩さずに座れる場所が限られる事に気が付いた女達の顔色が、一気に青ざめて行く。
板挟みになり、固まった女中達を追い詰めるかのように、のカウントダウンは淡々と続いた。
一人、また一人と女中達は庭に降りて玉砂利の上に膝をつく。
「はい、貴方と貴方の縁者だが信奉者だか知らないけど、腹心の部下以外が正座するまでに40秒かかりました」
廊下に残るのは女中頭と彼女の縁者らしき女中の二人だけだ。
対して玉砂利の上には二十人以上の女中が膝をついていた。
は一番近くに控えていた女中の前へ、己の足を差し出した。
先程池に女中を一人叩き落したせいで濡れているのだ。
拭けと言わずとも女は察したように懐から手拭を取り出した。
「し…失礼いたします」
震える声で拭き始めた女中をそのまま放置し、は廊下に立ったままの女中頭を見つめる。
縁がないからこそ、これまで自分に媚に媚びていた部下が、敵視した女に今度は平身低頭媚びている。
その事実は女中頭の自尊心を大きく傷つけた。
「あんたの親父さんさ。武家の人だって? でも私、あんたの親父を知らないのよ。って、ことはモブだよね?」
言わんとしていることが分からない周囲は怪訝な面持ちになるが、は気にせずに続ける。
「そんなモブ武将ごときの娘が、秀吉様自ら招致したこの私に盾突いて、嫌がらせして追い出そうって?
これまではわがまま放題甘え放題。アンタがパパに泣きつけばどうにかなったんでしょうけど、今回の事さぁ…
パパにお願いすればどうにかなるとか、思っちゃってる? 賄賂でも掴ませときゃどうにかなるって??」
は懐から美しい鼈甲の簪を取り出した。
「これ、素人の私でも分かる。この簪一本で、きっと村一つくらい買えちゃうよね?」
三成が顔色を変えた。
「これさ、三成さんがくれたんだけどさ」
足を拭き切った女中の髪にその簪をは迷いもせずに挿した。
「私には上手く使えないし、興味もないのよ。簪貰うより、夕飯に天ぷら出された方が私は嬉しいし。
でだ。あんたのお父さんは、私の機嫌を取るのに、この簪以上の物を差し出さなきゃならないと思うんだけど…
三成さんより立場が下のあんたのお父さんは、この私を相手に一体何を差し出すつもりなのかしらね?」
息を呑み続ける女中頭を真っすぐには見据える。
「私を追い出したい? いいわよ、出て行っても。でも秀吉様自ら招致した私が退職したら、私の指導係を務めた
二人はどうなっちゃうのかしらね?? 責任問題に発展するわよね? ボコボコにされるくらいじゃ済まない
んじゃない? 左遷もあり得るわねぇ? もっと最悪なケースだと、投獄とか?? 打ち首とか??
まぁ、なんでもいいけどさ。始末されるのは私じゃないから、知ったこっちゃないし?」
はさも楽し気に目を細め、詰る。
「敬愛してたはずが主の足引っ張るなんて滑稽よねぇ? それで何が、どこが傍仕え? 女中頭なんだか。
ああでも安心して? 温泉もあるし。今の所、私は出て行く気なんか更々ないからさ。
でももう私はあんたの顔見るのも声聞くのもうんざりなのよね。これはお互い様って事でさぁ。仕方ないけどさ。
そうするとどっちか目障りな方が消えるしかないじゃない?? でもさぁ、あんたの代わりはいくらでもいそう
だけど秀吉様自ら招致した私の代わりになる女って、どこにいるのかしらね??」
暗に退職勧告をしているのだと女中達は察して震えあがった。
この時代、婚期を逃した女達にとっては役職付きの城勤めという立場を失う事は、死刑に等しい。
首になどなれば世間のいい笑いものになるし、自ら辞職したとしてもに睨まれたこと自体が不味い。
―――大谷吉継の秘蔵っ子の算術士。
誰に言われずとも分かる。豊家に覚えめでたい女を敵に回せば必然的に立身出世は遠くなる。
そんな曰くが付いた女を娶ろうという物好きは、そうはいない。
が口にする脅しの一言一言の重みは、誅殺対象とみなされた女中達自身が一番理解していた。
そりゃ震えもするし、なんとか敵対対象から外されたいと願い、行動するというものだ。
そんな女中達の心中を知ってか知らずか、が求める事はもっともっと残酷で。
彼女達の想像を遥かに超えていた。
「言っとくけど、私貴方を首になんてしないわよ?
これから毎日、朝昼晩、気の向くままにネチネチネチネチネチいびりにいびり倒してあげる。
私に媚びたい女達があんたを苛めて苛め抜いて、苦情を申し立てても握り潰すし、それどころか賞賛してあげる。
辞めたいと思っても辞められなくて、いっその事死んだ方がマシって思ったら言って?」
許してくれるのかと女中達がを見れば、は心から楽しそうに微笑んだ。
「その時は宴の場で盛大な篝火の上に鉄板引いて、その上で鉄下駄履かせて死ぬまで貴方を躍らせてあげるから。
きっと楽しいわよ? 貴方が言うような下賤な民を楽しませる踊りと違って、命がけの踊りなんですもの。
見ものよね?」
の目の輝きを見た女中頭の縁者が唐突に庭先に飛び降りて玉砂利の上で土下座した。
「お、お許しください!!」
「どうぞ、これまでの無礼を平にお許しください!!」
「あんた達、何のつもりなの!!」
女中頭が叫べば、縁者はガタガタを震えていた。
「分からないの? 本気よ!? このお方は…本気で、させるつもりなのよ!!」
「当然でしょ? 私はね、やると言ったら絶対にやるわよ。
第一、用意するのは私じゃないし、踊るのも私じゃない。私は痛くも痒くもない。なんでやらないと思うのよ?
あんただって他人の痛みに今の今まで無頓着で好き放題して生きてたんでしょ?
今回はあんたが痛い思いする側になっただけの話じゃないの。何を今更動揺してるのよ。
せいぜい楽しみなさいよ。この状況を。それと先に言っとくけど、逃げようとか思わない事ね。
もし逃げたら一族郎党探し出して火炙りにしてやるから、首洗って待ってろ」
怒鳴り散らさず淡々と恫喝するの気迫に負けた女中頭は吉継を見た。
「吉継様! お助け下さい! この者は気が触れています!!」
「あらあらあら、図体だけでかい癖にどうしょうもないわね。分が悪くなると、速攻で男に泣きつくの??
でも残念ながらそれは今は意味をなさないんだな〜〜〜〜」
が廊下に上半身を預けて、吉継を見上げた。
「口出し無用。そっちの肩を持つなら、辞職します」
「辞職してなんとする?」
念の為とばかりに吉継が問えば、は「そうだな〜」と軽い調子で考えたふりをした。
「三成さんの所にでも再就職しようかな?」
「構わんぞ、今すぐでも」
即答する三成の口を、左近が横から塞いだ。
がここで三成を引き合いに出したのは、女中頭が三成派の女中達を囲い込んだからだ。他意はない。
今こうして三成がの言葉に逡巡することなく歓迎の意を示したことで、の地位がどういったものなのか、女中達に対しての体のいい布告になる。
正座したままの女達の顔色は今や青を通り越して土色だ。
「それは困る」
吉継が三成を見やって「渡せない」と言えば、三成が小さく舌打ちした。
二人の反応を受けて、が紡いだ言葉は妄言ではないと女達は理解した。
の背後には少なくともこの二人がいる。
を害することは、仕える立場の自分達にとっては百害あって一利なしだ。
「ほら、どうするの? 次は誰を頼るの? 味方はいないみたいだけど??」
孤立無援が確定した女中頭へのの追撃の手は緩まない。
|