|
「くー。官兵衛さんは手強いなぁ…何時か官兵衛さんにぎゃふんと言わせてやるんだから」
「ぎゃふん」
「そういう感じじゃなーい―!」
棒読みで答えた官兵衛に、が突っかかり、あっさり返り討ちにされた。
官兵衛がプンスコ怒るを見て、音もなく笑っていた。
三成が少しだけつまらなそうに視線を伏せる。嫉妬だ。
ひっそり支援しているから仕方ないとはいえ、の興味を他人に攫われることが悔しく、切ないのだ。
「しっかし…三成は安定しないのう」
分かっていて言っているのか、そうではないのか怪しい秀吉の言葉を受けて、三成の視線が微かに泳いだ。
疑われていると思ったのかもしれない。
「それは…その…」
珍しく言葉に詰まる三成のことを視線の端に留めもせず、は己の手の中の札を切った。
「大丈夫だよ、三成さんは慣れてないだけ。
今夜にでも私が個人授業するから、次、皆とやる時はめっちゃ強くなってるはずよ」
「何?」
「え?」
三成だけでなく、卓を囲む皆がの言葉に一瞬固まった。
「得手不得手ってあるとは思うんだけど、三成さんは明らかに理系だもん。
鍛えれば、絶対、強いプレイヤーになると思います。多分あれじゃない? 秀吉様と一緒に卓を囲んでるから
緊張してるとか、そんなところじゃないの?? あ、因みに私、ウノです」
の言葉を受けて三成がどんな反応をするのかと、皆の視線が三成に集まった。
様子を窺うように、ゲームの進行は遅々と進む。
「……その……俺は…」
「三成さんが、嫌じゃなければ…の話ですけど」
「嫌じゃない…よろしく、頼む」
「はい。楽しくゲームできるようになりましょうね〜」
軽い調子では言い、最後の一枚を場に切って、上がった。
「あ、ああ。そうだな」
今回も今回とて周囲からの宛の攻撃の防波堤になり切った三成は、親しい者が見たらくすぐったさを覚えるような小さな笑みを浮かべて、の申し出を飲んだ。
小さな一歩、されど大きな一歩はこうして踏み出された。
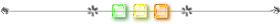
「こんばんは、そしてお邪魔します〜」
「あ、ああ…楽にしてくれ」
その日の夜、石田邸の三成の私室にがお手製のウノを携えてやってきた。
特別な関係でもない異性の部屋に、夜の帳が落ちた時間に足を踏み入れるのはどうなのか、と思わなくもないが、純粋な善意で講師役を買って出てくれているだけに退けにくい。
何より、懸想している彼からしたら親しくなる千載一遇のチャンスだ。逃せない。
「マンツーマン指導だと混戦では役に立たないかもしれないですが、三成さんほど頭のいい人なら
どうにか自分で出来ると思いますので、そこは気にしないことにしますね」
「うむ」
「やってて気が付いたんですけど、三成さんは攻撃系に弱いかもしれませんね」
の代わりに20枚分の札を引き取った時のことを言っているようだ。
『…まぁ…あの時手の中に『肆』を持っていはいたのだが…そういう事にしておくか…』
二人向かい合わせで手持ちの札を切りながらウノの戦略について話す。
とっくに自分なりの戦略も構築済みなのだが、素人の振りをしてのろのろと進めれば、その分といる時間は増えた。話すことはウノのことばかりだが、幸村が言っていた共通の話題が作れたことに変わりはない。
「…っと、結構いい時間になりましたね。今夜はこんなもんで切り上げますね」
「ああ、そうだな。ご教授感謝する」
丁寧にお辞儀をする三成に、は笑顔をもって「お粗末様」と答えた。
自宅となった離れに戻る際、は言った。
「もしよかったら、また明日の夜でもどうですか?」
「いいのか?」
「ええ、勿論! 三成さんがウノ楽しんでくれてるの、私も嬉しいから」
「そうか?」
「うん。秀吉様達にやられ放題だったから、嫌になっちゃったらどうしようかとちょっと心配だったんです。
でもこうして二人で遊んでたら、ウノの楽しさ知って貰えたみたいだから、それがとても嬉しくて」
「ああ、楽しいぞ。俺はあまり態度や顔に出る性質ではないが…とても楽しんでいる」
「本当ですか? ならよかった!」
「明日の夜、また同じ時間に…どうだ?」
「ええ、是非! それじゃ、お邪魔しました。それとお休みなさい!」
軽い足取りで離れに戻ってゆくの背を見送った三成は、自室に戻って襖と雨戸を締め切ると一人で声を殺してガッツポーズした。
『よっし!!!!』
にバレぬように初心者の振りをするのは多少面倒だが、その面倒を甘んじて受け入れてしまえば、あれだけ難渋していた二人だけの時間を堪能し放題だ。
この旨味に勝る苦労など、あろうはずがない。
「出来うる限り、遅々と精進するとしよう」
が目指すのは三成の脱!初心者だが、三成が目指すのはを凹ませない程度に勝ち、をニコニコさせて、二人きりの時間を出来うる限り長く持続させることだ。
やはり一人だけ着眼点が違う。
左近や吉継が知ったら呆れ果てて「何やってるんだ」と言いそうなものだが、残念ながらここに彼らはいない。
三成のこのズレ切った遊興の時間は、の善意につけ込む形で連日連夜続くことになった。
それが崩れたのは、かれこれ2ヶ月後。すっかりウノに魅せられた秀吉が一大ウノ大会を開催した日だった。
恐らく、これがなければこの先もずっとずっと三成にとっての天国のような時間は続いていたに違いない。
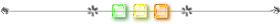
「秀吉様、マジでハマったんですね…ウノ…」
何時の間にか職人に言いつけて花札と同じ薄さのウノを作ってしまい、世に流通までさせていた秀吉のハマりっぷりにはドン引きだった。しかも自分がハマるだけでは済まさず、世にウノを奨励し始めてしまったから始末が悪い。
秀吉の影響で、ウノのプレイヤー人口が急速に増えて行く。
世の反応を受けて気をよくした秀吉は、身内で遊ぶだけにとどまらず、高札を使った大々的な試合の開催を呼びかけた。準備期間中には未経験者から初心者向けての講座まで開くという奨励っぷりだった。
尚講師役は利家・清正・幸村といった面倒見の良い面々の持ち回りだ。
肝心の会場はが芸事を披露する舞台周辺で、その地を借り切っての開催となった。
準備までに一月をかけて、開催期間は三日間。
閑古鳥が鳴くんじゃないかと想像していたの思惑に反して、ウノ大会は、謎の盛況ぶりだった。
開催地はあちこちから訪れた人で犇めき合っていて、時間帯によっては歩くのも大変だった。
ここまでこの催しが当たったのは、参加に特別な資格が必要にならなかったことが大きい。
天下に一番近いとされている男の好む遊びで、競技の歴史も浅いとなれば、第一人者になるのも夢じゃない。
そしてこの機会に秀吉の前で名を売りたいと考える者の、なんと多い事か。
名だたる学問所から派閥の威信をかけてエントリーしてくる文官から、軍略を収めたと自称する武士・軍略家、目敏い商人、立身出世を夢見る職人や農民までもが、このチャンスを逃すまいと、目の色を変えていた。
純粋にゲームを楽しみたいお子様にはいい迷惑である。
見世物としての一面もさることながら、お祭り大好きな秀吉の性格を反映するような出店の数々が軒を並べた為に、試合参加者以外の来訪も相まって、開催期間中は連日連夜の大盛況だ。
段々異様な光景になって来たな…と頭の隅で考えながらも、は三成に言った。
からすると三成は純粋に楽しむお子様組という位置付けだった。
「折角だから三成さんも参加しませんか?」
どれくらい腕が上がったかを知るのも一つの手だと言ってくれたには申し訳ないが、興味がない。
むしろ変にいい所を見せて、個人授業が終了しては堪らない。
だから三成は嘘くさい苦笑いを見せるに留めた。
「残念だ、開催側の任さえなければ参加したのだがな」
「そっか〜。三成さん運営スタッフなんだ」
「ああ、本当に残念だー。是非とも参加したかったのだがなー」
「殿…棒読みが酷いですよ」
から直接ウノを教えられた豊臣の将で参加しないのは三成くらいなものだが、三成のウノへの情熱はあくまでありきなのでしょうがない。
あの正則でさえ、直接教えられたから地区予選除外のシード枠として参加しているというのに、我関せずだ。
では何故そんな三成が、本戦当日になって参加者側に回ったのかというと、理由は単純だった。
大会本戦当日、公平性を保つ為に審判役を仰せつかったが座した席が不味かった。
「どうも! 総合審判の任を仰せつかりました! 木花咲耶です!
皆さん今日は公正な戦いを尊重し、相手に尊敬や賞賛をもって、真摯な意識で競技を楽しみましょう!
よろしくお願いします!」
試合会場を見渡せる席から宣誓したは、座る席を間違えた。
が座った席の横には、大会優勝者、準優勝者、特別賞受賞者への褒賞品が所狭しとばかりに並べられていた。
金一封や米や士官推薦枠の褒美の中に”お好きにして下さい”の一文が燦然と輝く屏風と茶の湯セット。
その茶の湯セットのど真ん中に涼しい顔をして座るのがだ。
誰の目から見ても、これでは豊臣が誇る稀代の舞姫を、”一晩”なのか”永劫”なのかは定かじゃないが、”好きなようにしていい”という誤解を生む。
「ちょ!?」
「御嬢さん!?」
「な! 何故そんなところに!?!」
「え、マジか!?」
「えええええ!?」
「…正気なのか…」
参加者全員が二度見せずにはいられなかった褒賞席。
そこに違和感なく座るを見た瞬間、石田三成は無言のまま立ち上がると当日参加者待機列に並んだ。
「ねぇ、お前様。あの子、座る場所間違えてるよ? 教えてあげなくていいのかい?」
こそこそと耳打ちをしてきた特別観覧席のねねに、秀吉もにんまり笑顔で答える。
「なぁに、大丈夫じゃて。三成が参戦したしのぅ」
「あら、あらあらあら、そうなんだね! 頑張るんだよ、三成〜」
「いい所、見せるんじゃぞ〜!」
秀吉夫妻の声援を受けて、三成は引き攣った。
「そっとしておいて下さい」
「緊張させないで〜!」
公平を掲げねばならないはずのが声を上げている時点で相当ダメな感じがする。
「三成さん、ガンバですよ〜!」
「あ、ああ…」
これで参加者の中に左近、吉継、官兵衛が居なければ三成とて本気になったりはしないのだが、残念ながら彼らは本気で参加しているから気は抜けない。
それに目を光らせねばならないのはあの三人ばかりじゃない。
なぜかこんな催しの時に限って上杉領から直江兼続が、毛利領からは小早川隆景が参戦してきた。
挙句、徳川領に流れたはずの藤堂高虎までもが当日参加者列に並んでいた。
無論幸村も正則も清正も利家も参戦している。
の人となりと三成との関係を知る者が最終的に勝者になれば何の心配もないのだろうが、万一が起きては困るから、三成は自らその万一の可能性を潰さずにはいられなかった。
「それでは本大会の予選を始めまーす」
各地の予選を勝ち上がってきた参加者が老若男女入り乱れてかなりの数になっている為、予選の座卓は20台。
そこに10人以上が集ってゲームを開始した。予選から勝ち上がれる者は1つの座卓から2人までで、次の予選で半数に勝者を絞る事になっている。
流石に吉継、官兵衛、左近、隆景が身を置いた各卓の決着は早く、彼らがサクサクと勝ち抜ける。
続いて清正、兼続、高虎、利家が勝ち上がった。
「あーーー!! くっそー!! きたねぇぞ!!」
「勝負の世界は非常なのだよ」
予選席の一角で吠えるのは正則で、正則を下したのは三成だった。
『…ははぁん、殿本気を出してますね?』
隣の卓を囲む左近が顎を擦り、最寄りの卓に居た幸村も目を見張った。
ここで三成、幸村、左近が勝ち上がる。
『正兄と三成さんは兄弟みたいなもんだものね…運に助けられたかな??』
審判業をこなしつつ、愛弟子認識の三成の戦績には気を配る。
「続きまして二回戦になります〜!」
名だたる将の勝ち抜けを、秀吉はそんなもんだろうと見守る。
そんな秀吉の視線の端に、意外な人物の姿が入った。
千利休、秀吉と懇意な茶人である。珍しい人が居たものだと、彼を知る人は目を見張る。
茶人がカードゲーム? と思われがちだが、褒賞の侘び寂の利いた茶器が利いたのだろう。
千利休、土気色の茶碗一つの為に参戦であった。
彼はの隣に置かれた茶器に熱い熱い視線を向けていた。
『なんだ? あの男…いやにを見ているな…』
褒賞席に熱い視線を送って憚らない利休を、三成が目端に留めた。
彼が求めるものは違うのだが、しか目に入っていない三成がその事実に気が付くことはない。
そんな千利休と石田三成が、二回戦で同じ座卓を囲んだから事は面倒になる。
同じ座卓に真田幸村と直江兼続がつくことになったが、スポーツマンシップに則ってゲームを楽しもうとしていた兼続と幸村が嘆くくらいには、卓は荒れた。
|