|
柔よく剛を制すタイプの利休、ピンポイントで利休を潰しにかかる攻撃性の塊の三成。
三成からの謎の敵意を、最初は利休も当惑しながらいなしていたが、三成の視線が自分と同じ褒賞席に向いていることに気が付くと目の色を変えた。お目当ての茶器を三成と争っていると勘違いしたのだ。
二人の間で始まる仁義なき戦いに音を上げたのは兼続と幸村だ。
頭の回転の速い男と心理戦に長けている茶人の戦いは想像以上に巻き込まれた者の精神を疲弊させた。
「あ〜、それはちょっとダメかな〜〜〜」
「え〜、そうなのか〜?」
「うん、ダメですね〜〜」
彼らが身を置く座卓とは対極の位置に、グダグダな戦いを繰り広げる比較的初心者寄りの卓がある。
別名「敗者復活戦・エンジョイ勢の集い」のフォローにが駆り出されていることをいいことに、三成、ここぞとばかりに持ち前の攻撃性を爆裂させていた。
『弐』『肆』を始めとした特殊札の応酬に巻き込まれた幸村と兼続が、自分の敗退を予見して降参の道を選ぶ。
「…こ、降参します……もう勘弁してください…」
「く……義がここで屈するというのか…」
「あの…利休殿……三成殿が欲しているのは茶器ではないと思います」
「え?」
降参する時、ぐったりした幸村は、肩からその場に崩れ落ちた。
彼の言葉は三成の肩を持つというより、恨み言に近かった。
「三成殿が欲しているのは…」
利休が視線を動かす。
自分の欲する茶器の傍に座って敗者復活戦の卓に声援を送りつつ審判するを見て、利休は眼前の三成を見た。
「もし。伺いたいのだが」
「なんだ」
「石田殿が勝者になった時、あの茶器の所在は何処へ落ち着くのであろうか?」
「……茶器? え、茶器って何の話だ??」
何とも言えない空気が、卓に舞い降りた瞬間だった。
「…私は茶器が欲しい。隣の女性は…興味がないが…茶器の行方は…」
「お前に譲ってやろう、勝手に持って帰るがいい」
三成の言葉を受けて、利休はいい笑顔で棄権した。
こんなことなら最初から言葉で解決してほしかったとは、余波でボコボコにされ続けた幸村と兼続の弁である。
こうして順調に勝者が決まってゆき、試合は準決勝になった。
観覧席に腰を落ち着けた兼続、幸村はそれぞれ友人に声援を送る。
「三成〜、頑張れ! 義が付いているぞ!」
「吉継殿、頑張ってください!」
「石田殿、頑張りなされ」
茶器目当ての利休も三成への応援を欠かさない。
はゲームをきっかけに三成に友人が増えたと喜んでいたが、そう言う話じゃなかった。
準決勝で三成と戦うことになったのは清正、利家、隆景、高虎だ。
「毛利家から代表で参りました。宜しくお願いします」
「徳川家を代表して参りました、秀吉殿! 家康様がよろしくと仰せでした!!」
小早川隆景と藤堂高虎―――天下人一番近いとされる男に、仕える主家を可愛がってもらいたい二人組。
参戦理由が恐ろしく分かりやすい。
「挨拶が済んだらさっさと帰れ」
「殿、余裕失い過ぎじゃーないですかね?」
「やかましい」
背後のもう一つの準決勝戦卓に付いている左近が苦笑している。
背中合わせに立つ主従の軽口は尽きない。
左近がいる卓は官兵衛と吉継と敗者復活で上がって来た正則と学問所の門弟がいる。
なんだかあっちの結果は始める前から目に見える気がした。
案の定、背後の卓の勝者は官兵衛、吉継、左近と学問所の門弟だった。
「うの」
では三成のついた卓がどうなったかと言えば、一言で言って泥仕合になった。
涼しい顔をしてえげつない手配を切る隆景と執念で食らいつく高虎の一騎打ちが延々と続いている。
運よく手札が1枚になった三成をそっちのけで、隆景と高虎は攻防を繰り返す。
偶に三成も余波で札を2枚取らされたりするが、基本はスッキプで飛ばされることが多い。
隆景と高虎の間に立っている弊害と言って過言ではなかった。
彼ら三人と同じ卓についている他の参加者も高度な潰しあいについて行けずに飽き始めている。
『これ…一体いつ終わるんだ??』
涼やかな笑顔の隆景の蟀谷で血管がピクピクしている。
血走った目の高虎の手に血管が浮き上がってくる。
その間で三成は遠い目だ。
『こいつらは…なんでさっきから俺を飛ばす?』
それは三成の手札が1枚だからである。
順当に勝敗を決した背後の卓が羨ましい。
観戦に回っている吉継や左近や官兵衛が昼食休憩をとっているのが、なんだかとても恨めしい。
『くそ…左近め…と一緒に茶を飲みおって……吉継! お前もなのか!!!』
まるでそこに居ない人のように順番を飛ばされ続ける三成があくびを噛み殺す。
「三成さん、頑張って〜」
「何をどうやって?」
本来なら心から嬉しい声援のはずだ。
想い人がわざわざ名指しで声をかけてくれたのだから嬉しくないはずがない。
が、無視されて手札1枚持ったまま30分も放置された三成は、つい率直な感想を述べた。
「殿、そこは素直に喜びましょうよ」
「どうやって??」
伏せられた札の山を使い切って、場に出そろった札の一番上だけを残して札をシャッフルして山札を形成すること三回、ようやく機は訪れた。
「上がりだ」
「あ!」
「おのれ、石田ァ!」
謎の潰し合いを続けていた隆景と高虎の攻撃をすり抜けて、三成が一抜けした。
「お疲れ様です」
流石にあれは可哀相だったと幸村に労われた。
利家と清正はまだ二人の戦いに巻き込まれている。
「はぁ……一体何だったんだ…今の戦いは…」
「でも良かったですね、隆景さんって人と高虎さんって人が潰し合ってる反面、利家さんと清正公さんもお互いに
潰し合ってたし、巻き込まれなかったのは運が良かったと思いますよ」
俯瞰で全てを見ていたの言葉を受けて、三成はそれもそうかと頷いた。
それから更に場の札のシャッフルを2回して山札を作った卓を制したのは隆景だった。
高虎は清正と利家を巻き込んで『弐』『肆』の応酬の末、自滅した。最後に自分が切った『肆』札のペナルティが回り回って自分に戻ってきてしまったのだ。
「ぐぅ!!!」
悔しそうに地面を殴りつける高虎の姿を見ながら、は冷や汗だった。
「いや…ただの遊びでそんなに悔しがらなくても……」
「まぁ、長丁場でしたしねぇ。集中力も切れて不思議はないでしょ」
左近が苦笑し、幸村が話題を変えた。
「次は決勝ですね、どのような結果になるのか、楽しみです」
善戦を讃えるように互いに握手してから卓から利家、清正、隆景が離れる。
高虎はまだ悔しがったままだ。
「続いて決勝戦になりますが、ここで1時間の休憩を挟みます」
想像以上に長丁場だった試合を考慮して、が休憩を宣誓した。
小腹を満たすなり、厠に行くなりしろという所だろう。
そういう事ならばと、一人また一人と、会場から離れて行く。
三成も先程の戦いでしこたま眠気が来たので目を覚ますべく顔を洗いに外に出た。
何せ次の試合で相手どらねばならないのは、官兵衛、吉継、左近、隆景だ。
他に二人自分のいた卓から勝ち上がった者が居るが、彼らは完全に幸運を味方につけただけだ。
高虎と隆景が潰し合い、高虎の自滅がなければ恐らく勝ち上がってくることはなかっただろう。
実際当人達もそれが分かっていたようで、決勝戦が始まると号令がかかった際には、棄権を申し出た。
参加賞に甘んじると述べた二人の勝者の目には、長期戦に持ち込みたがる隆景への恐怖がありありと浮かんでいた。
この結果を受けて、急遽、清正、利家が再浮上した。
自滅でその機会を逃した高虎が、再び悔し気に吠えた。
「…ええと…次回があるか分かりませんが、次回頑張りましょう〜」
が褒賞席から高虎を励ました。
「はい! 次こそは!!」
必要以上に大きな声で返事をしてから観覧席へ捌けて行く高虎。
想像以上に存在感のアピールはばっちりだった。
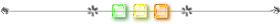
試合開始の銅鑼が鳴る前に、三成はを一度見上げた。
弟子が師に発破をかけて欲しがっているのかと思ったがそうではなくて、三成は何か、どこか、覚悟めいた熱く強い視線をに向けただけだった。
「開始!」
号令がかかり、決勝戦の火蓋が切って落とされた。
そこでは目を瞬かせた。
『ん? あれ? なんだろ…この違和感』
自分が鍛えるから強くなるとは言った。
だがたった二ヵ月ちょっとの夜の手習いで、ここまで急成長するものだろうか?
今眼下で繰り広げられている戦いは、一手二手先を読むといったような戦いじゃない。
互いが互いに数手先を読んだ戦いになっている。
誰かと誰かが同盟を組んでいるわけではないのに瞬時に連携が組み上がったかと思えば、次の瞬間にはそれが崩れて、別の新たな連携が生まれる。目まぐるしい事この上ない。
の読みでは官兵衛と吉継が頂上決戦の確定枠。要注意人物だ。
左近は手強いが、こうした場で執念を持つほど勝ちに拘るタイプに見えないから、隆景のような長期戦の鬼とぶつけると意外と早く飽きて戦線から降りるのではないかと思う。
では所謂敗者復活組の利家と清正はどうなのか? という話だが、彼らもこのメンツでは可もなく不可もなく、頂上決戦に食い込んでこないだけで中間争いに終始するように見えた。
隆景の人となりは分からないが、ゲームへの姿勢を見る限り防衛と冷静さに定評があるように思う。
気が長いタイプのようだから、もしかするともしかするのではないかと思っていた。
『え、あれ?』
だが全ての認識を改めなくてはならないとは思った。
に最下位争いの申し子だと思われていた石田三成は、被った猫を脱げば超攻撃型のプレイヤーだった。
中間争いに終始しそうな清正、利家の事は端から無視した。
同じ攻撃型の左近の相手は隆景に擦り付けて、早々に吉継、官兵衛との頂上決戦の場を作り上げた。
『嘘…三成さん、めっちゃ早いし…強い? え、何これ? どういうこと??』
小手先調べなんてものは一切ない。
本気の三成を相手にすることになった吉継と官兵衛の口元に満足そうな笑みが浮いた。
「ほほ〜。こりゃ凄い戦いになって来たのう」
秀吉が身を乗り出す。
「くっそ、マジかよ」
「うわ、模様変わった」
思うように場を維持できない利家、清正が山場再形成のシャッフルと同時に降参した。
二人が抜けたことで、カードの応酬の速度が上がった。
左近が苦笑いし、長期戦に定評のある隆景が僅かに眉を寄せる。
「お三方ノリノリですねぇ」
「…まぁ…どうという事もない」
「どうした、疲れたか?」
「棄権ならばいつでも受け入れるが?」
涼しい顔をして札を切り続ける三成、官兵衛、吉継。
誰か一人の相手ならばまだしも、この三人を相手にするのは骨が折れると、左近は見切りをつけた。
ただ左近は自分一人で離脱する程素直でもなかったようで、自分の手持ちの中の特殊効果の札を使い切って隆景を巻き込んで棄権した。隆景憎しではなく、単純に巻き込めるならば相手は誰でも良かったらしい。
回り回って襲い掛かって来た『弐』『肆』のペナルティで、一人だけ凄まじい数の手札を持たされることになった隆景は苦笑するとともに、棄権を受け入れた。
「いやはや…良い勉強になりました。腕を磨いて出直します」
長期戦をいくら好んでも、頭脳派の三人を相手に両手に余る札を抱えては浮上は見込めまい。
何より棄権した時に秀吉に「災難じゃったの〜」などと、直接声をかけられたから、毛利家をアピールするという本来の目的はしっかりと果たせたはずだ。
「さて…ここからは…遠慮はいらぬな?」
官兵衛が三成を真っすぐにねめつけた。
ウノ初回チャレンジの際、秀吉のバックアップを邪魔された件を根に持っているのが見え見えだった。
ピンポイントで叩く宣言に近い官兵衛の言葉を三成は涼しい顔で受け流した。
「何のことでしょうか」
言葉とは裏腹に三成からの官兵衛への攻撃は止まない。
をピンポイントで狙い続けた事への報復である事が、狙われた当人を除いて、同じ卓を囲んだ経験のある者にはヒシヒシと伝わった。
「吉継〜、棄権してもええぞ〜」
よく分からないが、何か尋常じゃない経緯が官兵衛と三成の間に発生していると察したらしい秀吉が声を上げる。
「善戦するだけしてみます」
本気の三成と官兵衛を相手に軍略を試せる機会など滅多にないと、吉継は微笑み続ける。
「えーと…必要ないかもしれないけど…吉継さん頑張ってー」
一応上司だし…とお愛想的な発想でが声援を送る。
「、愛弟子を叱咤しろ」
『でないと嫉妬で俺が狙われる』
卓から目を離さずに吉継は札を切った。
官兵衛の視線が僅かに動き、三成の視線も動く。
「いやはやすさまじいのう。互いに互いの手を読んどるわ」
「え、手持ちの札、分かってるってことですか??」
「おそらくのぅ。誰の手持ちにどの柄と特殊札があるかくらいの予測は付いとるじゃろ」
「えええええ!? 何それ!? もうウノじゃない戦いになってる!?」
正にその通り。カードゲームの形をとってはいるが、三人の応酬は心理戦の様相となって来た。
「はぁ…残念じゃのう」
「何がですか?」
白熱する戦いを見守りつつが問えば、秀吉はくしゃりと顔を崩した。今にも泣きそうだ。
「ここに半兵衛がおったら、もっと盛り上がったと思うんじゃがのぅ」
寿命ばかりは誰にもどうにも出来ないと小さく肩を落とす秀吉に、かけてやれる言葉をは持ち合わせていない。
「私がおりますれば、豊臣の世は安泰ですがご不満ですか」
気持ち硬い声が官兵衛から漏れた。
「ちゃうちゃう! 早期決着が見たいんじゃないんさ! おみゃーさんらと戦う半兵衛が見たかったんじゃよ!」
裏表のない回答に、官兵衛は満足そうに寄せた眉を緩めた。
秀吉ガチ勢の官兵衛を揺さぶる秀吉の弁、その小さな小さな隙を吉継・三成は見逃さなかった。
二人は即興で連携を組んで官兵衛の足元を崩しにかかった。
「…全く、卿らは抜け目のない…」
一瞬の隙がこの二人相手では命とりだとばかりに官兵衛は顔を引き締める。
その辺の軍師であればここで諦めるのだろうが、そこは官兵衛。一筋縄ではゆかない。
|