|
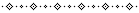
自身に課せられた重責を自覚して床に伏せてから数日後、は回復した。
家康の支えもあってか、余裕を取り戻したは、以前にも増して意欲的に政に取り組むようになった。
の中に、起きた大きな変化。
それを目の当たりにした左近、慶次、幸村は気を揉んでいたが、肝心のから詳しい経緯が話される事はなかった。
「ごめんね、皆…でも、まだ時節が足りない…ごめんね…」
視線を伏せて、心底申し訳なさそうに語ったにそれ以上の無理地をする事は出来ない。
彼ら三人を始め諸将は、時が満ちるのを待ちながらの負担を減らすべく、日比研鑽するしかなかった。
きっかけとなったあの包みは、あれからが触れてもに変化を齎す事はなかった。
あれはが示唆したように自身の私物だったようだ。
「ほら、ここにイニシャル」
示された通り、包みの裏には西洋の文字で彼女の名が刻まれていた。
何故それがここに? どういう意図を持って現れたのか? それはまだ誰にも分からない。
けれどもそれを手にした事で、がほんの少し安らいだ顔をしているという事実がある以上、家臣一同、がそれを持つ事に否を唱えようとは思わなかった。
人材を検分し、増えた土地へと的確に配置してから月日は流れて、ある日の事。
「は〜、暇だな〜」
文机を前に両肘をついて広げた掌に己の顔を乗せたが呟いた。
の声を聞いた左近と兼続が同時に顔を上げてを見やる。
不機嫌なのが一目瞭然という体のは、今度は机に突っ伏して、掌を握ったり閉じたりと、どうにもこうにも忙しい。
「はー。なんかなぁ………やってらんないよ…もう…」
どうやらは考えている事、特に不満等は、無意識の内に口に上る性質のようだ。
左近と兼続が非常に居心地が悪そうな眼差しを向けている事に、これっぽっちも気がついていない。
「うちって……これって人、いないんだよなぁ…」
ぐしゃぐしゃと己の頭を掻き回すの声は不満と悲壮の色が強く現れている。
こんな声を発していた事を知れば、他の将、特に幸村はショックで寝込んでしまうかもしれない。
だとしてもの中に燻る感情は、そう易々と昇華出来るようなものではないようだ。
延々と似通った不満を漏らし続けている。
「どっかに落ちてないかな〜」
『…やれやれ…』
そんなを横で眺めていた左近は一つ溜息を吐いた。
そもそも貧困からの脱出を最たる目標にしていた家は、徳川勢の突然の全面降伏を受けて、あっと言う間に赤字国家から脱却した。
それと同時に領地が増え、人材が増え、財源が増えた。
中でも治世に強い家康、曲がった事が大嫌いな浅井長政、文武に長ける徳川一門を配下にした事は大きい。
それだけでも大きな財産だと言うのに、日頃の行いの良さが幸を奏した。
仕えるべき主を求めて在野を流離っていたあの服部半蔵が、妻のたっての哀願に根負けして帰順したのだ。
家康の才で財政のやりくりを卒なくこなし、治安改善が浅井夫妻の手で確固となり、諜報活動から防衛までを幅広く担える半蔵率いる伊賀忍軍団のお陰で、外敵への睨みも大幅に利かせられるようになった。
ついこの間まで赤字と格闘していたとは思えぬ躍進だ。
元々が打ち出していた政策のシンプルさも良かった。
誰の目から見ても分かりやすい政策。民と共にやって行きたいという現代の平和思想丸出しのの政策は、土着の民に支持されており、帰依した新しい土地の民にも感謝こそされ、反意を持たれる事はなかったのである。
そんな新生家の当面の問題は、家の善政を聞きつけて流れてくる民の住む場所と仕事の確保と、それを難なく捌く事務方の人材補強であった。
人材面の問題は二の次にするとしても、は移民問題でも思想が柔軟だった。
使われていなかった武家屋敷の幾つかを整備し、そこで職業の斡旋と、家を持つ為の相談が出来るようにしたのだ。
これと同時には各都市に医療所を設けた。人が流れると言うことは、時として病も流れ着いてくる。
だから先手を打った。年中無休、二十四時間営業を目指して、国お抱えとしてスタートさせた医療所の評判は上々で、それなりに繁盛している。お陰で、求人も増える。
治療に当たれる医術者、看護士、これらは特別な知識がなければ話にはならない。
けれども薬の運搬や道具の調達、備品の生産と、何かを始めればそこから派生する需要は大きく跳ね上がる。
その点を考えれば、の対応は迅速だったと言っていいはずだ。
「はー……本っっっ当、暇……暇すぎる……」
手にした土地全土の安定が一定水準まで得られるまでは戦はしない。
そう決めた今の家は近隣諸国ともそれなりの連携を取っている為、戦への憂いはない。
あるとすれば以前暗殺を企てた東国を納める北条が挙兵するかどうかという不安だけだ。
だがそれとて、さしたる大きさの懸念ではない。
敵が一ヶ国と分かっているだけに、目を光らせやすいからだ。
北条に何らかの動きがあれば、半蔵が逐一知らせてくれる事になっている。
適材適所、"任せられるべき人材に全てを託す"がモットーのが差し迫って不安に思うような事は、今は何一つない。つまり最近のは、こうして文机に括りつけられてばかりいる。事務処理一辺倒だ。
慣れぬ筆で悪戦苦闘していた書類整理も、限界を訴えたが印鑑を作ってしまった事から迅速に進むようになった。
そうなると拘束される時間はあれどする事は同じで、飽きたと訴えるのも無理はないのかもしれない。
「そりゃねー、最初慶次さんや左近さんを見た時は、喜んだよ? 内心ドッキドキで小躍りしそうだったよ?
でもなぁ……やっぱ、現代人に比べたら、もう全っっっっ然、話にならない。そう、なんないんだよ〜」
名指しで落胆されると、それはそれで気にもなるし凹みもする。
左近は顔に明らかな苦渋を貼り付けたが、彼女の独り言が止む気配はない。
『分かっちゃーいるんですけどね……これだけ立て板に水とばかりに続くと、なんというか…傷つきますな』
この世界に降りてから、慣れぬ事を自分なりに全力投球でやってきたの事だ。
そろそろ鬱積を溜め込んで音を上げてくる頃かもしれないと踏んでいたが、ついにきたか。
しかも彼女が漏らした不満に自身の名まで含まれていようとは。
どうしたものかと、左近は動かしていた筆を止めて思案する。
「……はー」
は溜息を吐いて、机の上にあの牛皮製の包みを置いた。
中に何が入っているのかは分からないが、しゃらんと心地よい金属音が鳴る。
最近のはそれを指先で撫でては溜息ばかりを吐いている。
「…政宗さん、兼続さん、幸村さん、長政さん、市さん、家康様だって、論外だったもんな〜。
どっかにこう、私がビビビッ! っと来る人はいないかな〜。はー、現代が恋しい……」
ついに涙声。
見守る左近の眉間には深い皺。
これ以上は見ていられないと、兼続が席を立つのと同時に、の背後に屋根裏から影が舞い降りた。
「忠信」
「あ、半蔵さん! お帰りなさい、どうしました?」
声を聞いて顔を上げて、すぐに振り返る。
意識を切り替えたのか、の表情には、もう不満はない。
「北条、攻めに着手。尖兵、城を出立」
「そっか、ありがとう。引き続き見張りお願いします」
「御意」
消えた半蔵から立ち上がっていた兼続と左近へと、の視線は移る。
「兼続さん、厠ですか? だったらついでに帰りに臨時召集お願いします」
自分の愚痴の為に兼続が立ち上がったとは思っていない様子の、実に暢気だ。
「いや…そうではなく…」
「はい??」
決してそういう事ではないと、言いかけて兼続は止めた。
机の上に並べた牛皮の包みを帯へと忍ばせて立ち上がったには、先程までのくさくさした雰囲気はない。
となれば、それ以上の言葉は、今は無意味だと彼は判じた。
「いや、なんでもない」
「そうですか? じゃ、頼みましたよ」
評議場へと向かうべく、室を出るの後に左近が続く。
それから一刻と経たずに、評議場に諸将が集った。
「皆さん、おはようございます。何時もご苦労様。早速ですが、北条が動きました。迎え撃つ事になります」
挨拶は軽快に、用件は手短にがモットーのが開く評議は何時も短時間だ。
「で、今回の陣容です」
広げた地図の上へと、木で作った駒を一つ一つ、乗せて行く。
「前線、慶次さんと長政さん。幸村さんと兼続さんは街道へ布陣。本陣守り、左近さんに半蔵さん。
後援は家康様と徳川一門でお願いします」
「おいおい、この程度の事にこんなに出すのかい?」
向こうも小手調べでしかないのではないかと問う慶次に答えたのは左近だった。
「姫は今の軍の動き全体を把握したいのさ」
なるほどと幸村、兼続が頷く。
「ちょっと待て!!」
「あ、あの…」
名前が上がらなかった政宗と市が声を上げる。
「はい?」
「儂の名がないぞ」
「ああ、お二人には城に残り、国元の守護についてもらいます。
同盟を何時どこが破棄してくるか分からないし、破棄しないまでも、お手透き状態の足元で妙な情報の
流布でもされたら、それこそ堪らないし」
立て板に水とばかりに答えて、はにんまりと笑う。
「そんな訳で、国許守護は身軽さを兼ね備えた政宗さん、市さん、伊達軍、伊賀忍の皆さんに任せます。
これって機動力が物をいう重要な仕事ですよ、宜しくお願いしますね」
さり気ないやりとりで、相手の士気を上げる事も忘れない。
処世術の一つだが、この時代の人間にそんな事が分かるはずもない。
一声添えられた二人は俄然、目に優越感とやる気を宿す。
人心掌握術にどこまでも長けた人だと、左近は内心で関心し頷いた。
「今回は出撃部隊に、少数ですが騎馬と弓兵が入ります。
歩兵ばかりではない戦がどんなものになるのかは分かりませんが、皆さんの奮戦に期待しています。
それじゃぁ、準備に掛かりましょう!!」
解散の号令が掛かると同時に、側近は悟った。
どうもは今回も同行するつもりらしい。
止めようともこの様子では聞きそうもないだろうな…と、諦めが半分、どうしても止めねばならないとの思いが半分。
彼らは弁の立つ左近に訴えさせるべく、視線を向けた。
「姫、陣羽織用意させましたんで、着て下さいね」
「はーい」
当の左近は暢気で、送られた視線に潜む意図を汲み取る事はなかった。
止めるつもりは左近には一切ないのだと悟った残留支持派の幸村、兼続、家康、長政は四人同時に肩を落とした。
そんな四人に後から慶次の明るい声が掛かる。
「まぁ、そう気を落としなさんな。俺らが食い止めりゃ、問題はないさ」
「…そうですね…」
がっくりと頭を垂れている幸村には悪いが、の気分転換になればいいと左近は考えていたようだ。
その軽率な考えが、戦場にあってあの惨劇を生み出すことなど露知らず。
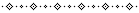
決戦の地に入ってから、相手の陣容を知った左近は、渋い顔をした。
敵軍が奇策にかけては天下一のあの豊臣秀吉とその愛弟子石田三成で構成された豊臣一門だったからである。
『…まさか大殿や殿と見える事になるとは…』
けれども新品の陣羽織に身を包み、隣に座るを見ていればそんな感傷に浸ってもいられない。
女性用と言う事で軽めに作らせた陣羽織。
それでも重いのか、は息苦しそうで、ふぅふぅと荒い呼吸を繰り返している。
「ねぇ、これってさ、こんなに重いんだね」
「すみませんねぇ……これも再検討の必要ありですな」
「…そうみたいだね…ところで、敵さんは?」
「…今回は手強いかもしれません」
「そう…」
陣中央に腰を降ろすをちらりと見て、視線で「怖いですか」と問えば、は首を横に振る。
「大丈夫、ドキドキしてはいるけど…左近さんと半蔵さんがいる限り、本陣陥落はないだろうし。
皆の事を信じてるから、怖くはないよ」
はにかむように微笑むが眩しいとばかりに、左近は目を細める。
その目には、をなんとしても守りぬくと言う気概があった。
「では、左近の軍略、お目に掛けましょう」
左近が陣中に前線に進み出て、軍配を振り上げた。
再編成された自軍の動きを見極める意味を持つ防衛戦の火蓋が、今切って落とされた。
|